0を1にするアウトリーチ活動
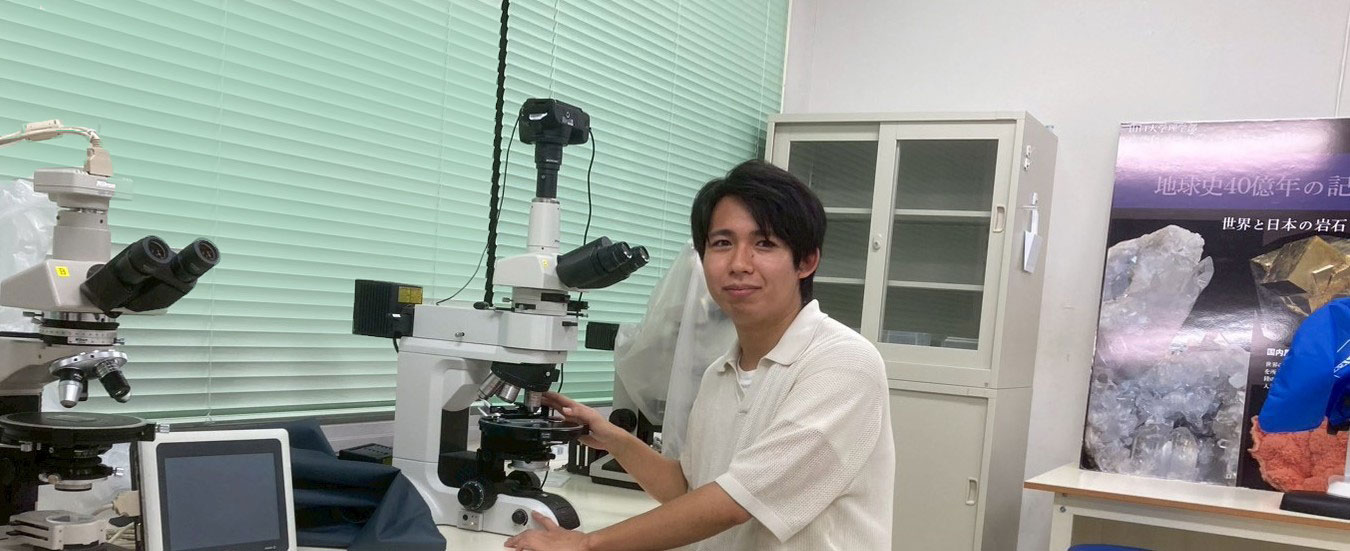
学生の今
Students
Now
内山賢太 さん
理学部 地球圏システム科学科
0を1にするアウトリーチ活動
中高生向けフィールドワーク型イベント「山大生の地学探検教室」を企画
なぜこのイベントを企画をされたんですか?
地学を専門に学ぶ学生が全国的に減っているんです。日本は地震や火山噴火、土砂災害など自然災害が多く、地盤の性質や地下構造を理解することは暮らしや社会を守るうえで欠かせません。インフラの老朽化も進む今こそ、地学の専門知識はますます必要とされているのに、学ぶ人が少なくなり、将来的な人材不足が心配されているのです。
その大きな理由のひとつが、中高生が地学に触れる機会の少なさだと思います。小学生のころは科学イベントなどで自然に親しんでいても、中学・高校になると授業の中で地学に出会う機会が激減し、興味を持つきっかけを得られないまま進路を考えることになるのです。
だからこそ「まずは知ってもらいたい」と考え、中高生を対象としたフィールドワーク型イベントを企画しました。それが、「山大生の地学探検教室」なんです。
0を1にするアウトリーチ活動
 当日はどんなことをしたんですか?
当日はどんなことをしたんですか?
当日は中高生16名と共に、山口県を代表するジオサイトである畳ケ淵と須佐ホルンフェルスを訪れ、フィールドワークを行いました。
畳ケ淵では、柱状節理が発達した溶岩流を前にその成り立ちを説明し、参加者には自由に観察や記録をしてもらいました。続いて訪れた須佐ホルンフェルスでは、砂岩と泥岩がつくる縞模様をスケッチし、グループで柱状図を作成しました。そこで「層の幅はなぜ違うのだろう」「粒度の差はどうして生じるのだろう」と問いかけると、自然に議論が始まりました。最初は関心が薄そうに景色ばかり眺めていた子が、最後には夢中でスケッチに取り組んでいた姿がとても印象的でした。自分の手で地球を読み解く体験は、参加者たちにとって新鮮な刺激になったと思います。
フィールドでは観察やスケッチに加え、私たちが大学で学んでいる地質調査についても紹介しました。地下構造や土質、地下水の状態を知るには、ボーリングや地震波探査などの手法がありますが、基本となるのは地表を歩いて情報を集める「地質踏査」です。実際に現地を歩き、岩石や地層の情報を丁寧に集め、集めた情報をもとにさまざまな分析を行います。今回の体験を通じて、参加した中高生のみなさんにも、大学での学びの一端を感じてもらえたのではないでしょうか。
地学は普段触れる機会が少ない分野です。だからこそ、まず“0を1にする”こと・・・つまり、興味を持つきっかけをつくりたいのです。
私たちの好きな地学の楽しさを知ってほしい
地学の魅力って、どんなところですか?
地学の魅力は、その幅広さとスケールの大きさです。岩石や鉱物、古生物、気象、天文まで幅広く扱い、46億年という長大な時間の流れで物事を考えます。物理や化学、生物の知識を組み合わせながら、目の前の岩から地球全体の成り立ちへと事象がつながっていくプロセスは、いつもわくわくさせられます。フィールドで「この構造はどうやってできたのだろう」と考えながら歩き、手がかりを見つけたときの達成感は、何にも代えがたい喜びです。
これからの展望は?
今回のイベントは少人数でしたが、地学に関心を持つきっかけを提供できた手応えがありました。地学は面白く、そして社会に不可欠な分野です。だからこそ、その魅力を伝えることから始めようと思っています。
私たちが好きな地学の楽しさを知ってもらえれば、それが選択や将来の学びへとつながるかもしれません。今後も活動を続け、将来的には、全国の学生や研究者とも連携して、より多くの地域でこうした機会が広がっていくことを願っています。

一緒に活動しているメンバー
左から、一井新さん、内山賢太さn、福田昴生さん、土田和輝さん
