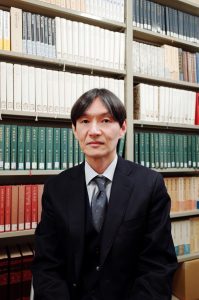研究科長あいさつ
研究科長のメッセージ
|
東アジア研究科長 森野 正弘 |
21世紀は東アジアという地域が焦点化されることになるのではないか。そして、その動向は日本の将来を左右することにもなるであろう。このような 未来予測のもとに、東アジアという地域が直面する課題、あるいはそこに伏在する問題を探究するべく、2001年4月に博士後期課程の独立大学院として東アジア研究科は開設されました。現在、開設から20年あまりが経過し、研究対象とする地域もアジア全般へと拡がりを見せています。本研究科では、アジアの歴史・文化・社会に関する研究を行う「アジア比較文化コース」、アジアの地域特性や社会経済に関する研究を行う「アジア経済・経営・法律コース」、アジア地域の教育問題を解決するために理論的・実証的研究を行う「アジア教育開発コース」を設置して、学生の研究課題や修了後の進路に応じた教育体制を組み敷いています。
アジアが抱える問題は複雑で、基層にある文化の多様性とも相俟って多岐にわたります。アジアに特有のこのような諸問題に対処するためには、複眼的な視野と柔軟な思考力が欠かせません。本研究科の特色の一つである共同型の演習は、そういった能力の育成をカリキュラムとして実装したものとなります。様々な専門分野の教員たちと議論を交わす経験は、隘路を打開するための良い機会となるでしょう。と同時にそれは、自らの専門を顧みるきっかけともなるはずです。私たちはまず、ある特定の専門性をもった研究者として存在するべきであり、学生にもそれを求めたいと思います。
刻々と変化する社会の情勢下にあって、潮流を読む力は今後更に必要とされるかもしれません。しかし、それ以上に大切なのは各々の専門分野において錬磨されてきた固有の思考法を内面化し、それに準拠して物事を判断する力です。かつて近世の国学者である本居宣長は、江戸幕府の政策によって儒教的イデオロギーが世の中に浸透するなか、『源氏物語』を「儒仏などの書にいふ善悪」の観点で読むのではなく、「もののあはれ」を理解するための書として読むべきだと説きました。すべての事象を〈善/悪〉で腑分けする慣習に警鐘を鳴らしたのです。誰にも阿るでもなく、ただ学問に準拠して正否を判断すればよい、そのような世の中の実現へ向けて東アジア研究科は在り続けたいと思います。